はじめに:日本の気候こそ要注意。湿気対策は必須!
日本の気候は、高温多湿で雨が多いことが特徴です。特に梅雨や台風シーズンの時期は空気中の湿度が高く、地域によっては床下や外壁周りが長期間ジメジメとした状態が続くことも珍しくありません。こうした湿気こそが、木造住宅の大敵になる可能性があります。
なぜなら、床下や壁内に水分が入り込みやすい環境だと、カビやシロアリ、木材腐朽といった深刻なリスクが高まるからです。住宅を支える土台や柱などの構造材が傷んでしまえば、家全体の耐久性が損なわれ、長期的に見て補修費用もかさみます。こうした被害を避けるためには、基礎工事の段階からの防湿・防水対策が極めて重要です。
ただ、実際の建築現場を見ると、「防湿シートを敷く工程をスルーしていた」「配管の周囲をシーリングせずに放置していた」などの不備・手抜きが原因で、数年後に床下から問題が発覚する事例が散見されます。工事費のコストカットや知識不足、スケジュールの圧迫など、さまざまな背景要因によって対策がおろそかにされることがあるのです。
本記事では、床下の湿気対策を怠った結果どんなトラブルが起こりうるのか、なぜそのような対策が省略されがちなのか、放置するとどうなるのか、そして施主としてどこをチェックすべきかを解説していきます。近年(過去10年ほど)も木造住宅の湿気由来のトラブルは依然として報告例がありますので、「湿気は家の天敵」という意識をしっかり持って、安全・安心な住まいづくりを目指しましょう。
具体的なトラブル例
(1) 防湿シート未敷設 or 破れ放置
●布基礎の場合の基本プロセス
布基礎では、本来、地面からの湿気を遮断するために防湿シートを敷き詰め、その上に「捨てコン」と呼ばれる薄いコンクリートを打設するのが一般的な工程です。こうすることで、地面から立ち上ってくる水分や湿気をシートがブロックし、床下が湿気にさらされにくい環境を作れます。
ところが、何らかの理由(手間やコスト削減など)で「シート敷き込み」を省略してしまったり、シートが破れたまま放置されているケースが見受けられます。そうなると、土壌からの水蒸気が床下に直接上がってきてしまい、結果的にカビやシロアリ被害のリスクが高まるのです。
●起こりうる問題
- 床下が常にジメジメ: カビが繁殖しやすい環境になる。
- シロアリ侵入のリスク増: 湿度が高い床下はシロアリにとって格好の生息環境。
- 土台や大引きの腐朽: 木材が長期間湿気にさらされることで腐食が進む。
- 補修が大変: 新築後にこれを発見すると、床下に潜り込んでビニールを敷き直す工事が必要となり、費用と手間が大きい。
(2) ベタ基礎でも隙間がある
●ベタ基礎の特徴
ベタ基礎は、布基礎と違って地面をコンクリートで広く覆うため、一般に湿気対策としては優秀だとされています。国土交通省や建築関連団体も「ベタ基礎は床下の地盤面からの湿気をかなり抑制できる」と評価しています。
しかし、**「ベタ基礎だから絶対安心」**というわけではありません。コンクリート打設の際に生じる継ぎ目(打ち継ぎ部)や、配管スリーブの周りから雨水や地下水が侵入する可能性は残ります。直近10年ほどの建築トラブル事例にも「ベタ基礎の打設工程での不備が原因となり、床下に漏水」した報告が散見されます。
●典型的な隙間と原因
- コンクリートの打ち継ぎ面: 時間をあけて複数回に分けてコンクリートを流す場合、そのつなぎ目が弱点になり、そこから水がしみ出すことがある。
- ひび割れ(クラック): 施工時の気温や湿度管理が不十分だと、コンクリートが硬化する過程でひびが入り、水分が侵入するルートになる。
- スリーブ周りのシーリング不備: 配管を通す穴を埋めるシーリング材が適当に塗られているだけだと、台風などで大量に雨水が押し寄せたときに浸水しやすい。
(3) 配管スリーブ周りの防水処理ミス
●スリーブとは?
基礎や壁に開けた配管用の貫通穴を「スリーブ」といいます。給排水やガス、電気ケーブルなどを通すために必要ですが、このスリーブとコンクリートの隙間をしっかりと防水・気密しないと、水や虫が簡単に侵入してしまいます。
●放置するとどうなる?
大雨の際や台風による吹き込みなどで、スリーブの隙間から床下に浸水する可能性があります。また、ゴキブリやシロアリ、あるいはナメクジなどが床下に入り込みやすくなることも。特にシロアリは数ミリの隙間があれば十分侵入経路になるため、配管まわりのシーリングが甘いと、土台や柱への食害が数年後に発覚するという事態も考えられます。
なぜ起こる? 防水・防湿手抜きの背景
(1) 経費&手間削減
工事費を抑えたり工程を短縮するために、防湿シートやシーリング材、防蟻対策の薬剤処理などを省いてしまう業者が一部存在すると報告されています。こうした行為は、施主からすれば「多少安くなる」メリットはあるかもしれませんが、数年先・数十年先のリスクを考えると大きなデメリットとなるでしょう。
(2) “ベタ基礎だから大丈夫”という誤解
ベタ基礎が湿気をかなり防いでくれるのは事実ですが、完璧に施工されていなければ機能しません。打ち継ぎや配管周りなど弱点は必ずあるので、そこをいかに処理するかが大切です。誤った思い込みで「ベタ基礎なら水なんか入らない」と考えてしまい、施工管理を怠るケースがあります。
(3) “室内に断熱材”だけで安心してしまう
最近の住宅は断熱性能が向上しており、「断熱さえしっかりしていれば家は快適で長持ち」だと思われがち。しかし、断熱材を入れるだけでは床下や基礎周りの湿気までブロックできるわけではありません。実際、床下が高湿状態になれば、断熱材自体が濡れて性能低下を起こす事例も報告されています。
放置するとどうなる?
カビ・ダニ・シロアリ大発生
床下が湿気で満たされた状態が続くと、カビが生えやすくなります。そのカビをエサとするダニが繁殖し、さらに木材を食害するシロアリのリスクまで高まるという悪循環。過去10年以内のトラブル報告でも、床下が過湿状態だった家でシロアリ被害が発覚し、土台のほぼ全域を交換する羽目になったケースも見受けられます。
構造材の腐朽・劣化
土台や大引きなど、湿度に長期間さらされる構造材が腐ってしまうと、家の耐久性が大きく損なわれます。とくに日本では雨の多い年が続くこともあり、数年のうちに腐朽菌が広がってしまうことも珍しくありません。腐朽が進むと交換費用が高額になり、最悪の場合は住宅の安全性を大きく揺るがす事態になりかねません。
悪臭・健康被害
カビや雑菌が増えると、床下から嫌な臭いが上がってくることがあります。さらに、カビが原因でアレルギーや喘息などの症状を悪化させる例も指摘されており、室内環境の悪化は住む人の健康に大きく影響します。
どこをチェックすればいい?
(1) 防湿シートの存在&状態
布基礎の場合は、地面に敷くビニールシートがきちんと使われているか、重ね合わせが十分か(規定の重ね幅があるか)、破れがないかを確認しましょう。すでに捨てコンを打った後だと見えなくなるため、施工写真を残してもらうよう依頼すると安心です。
ベタ基礎なら、一面のコンクリート盤に隙間や大きなクラックがないかがポイント。こちらも施工写真を確認するか、工事中に現場を見学しておくと良いでしょう。
(2) 配管スリーブ周りの防水処理
配管と基礎コンクリートの隙間をシーリング材などで塞いでいるかどうかを確認します。施工会社が写真を撮っていれば見せてもらい、雑に塗りつけただけになっていないかチェック。基礎周りに水が溜まる地形の場合、余計に入念に対策する必要があるため、排水計画や勾配についても説明を受けるのがおすすめです。
(3) 仕上がり&引渡し前の床下点検
可能であれば、引き渡し直前に床下を覗ける機会を作ってもらいましょう。雨の日の翌日や台風シーズン後など、外が湿気ているタイミングに点検できるとより実情を把握しやすいです。ここで水溜まりやカビ臭、虫の死骸などが確認された場合は、その原因を施工会社に尋ね、適切な補修や再処理を要求しましょう。
対策・疑わしいときの処置
(1) 防湿シート+捨てコン&ベタ基礎の確立
設計段階で「床下の湿気をどう遮断するか」を明確にしてもらいましょう。布基礎の場合、防湿シートを丁寧に敷き、捨てコンを打つ工程が必須です。ベタ基礎でも配筋やコンクリート打設に際して隙間を作らないよう厳格に管理する必要があります。
(2) 配管まわりのシーリング施工
どのようなシーリング材を使い、どういった手順で施工するのかをあらかじめ確認しておけば安心です。実際に雨が降った後の現場見学や、施工写真の提示を求めることで、手抜きがないかある程度チェックできます。
(3) 後付けの防湿・防蟻工事
すでに建物が完成している場合や、中古住宅を購入して床下に問題があると判明した場合でも、後からビニールシートを敷き直したり防蟻剤を散布したりといった補修は可能です。ただし、大掛かりな工事になることもあり、完全な理想状態に戻すのは難しいケースもあります。それでも対策しないよりは遥かにマシなので、気づいた時点で早急に専門家へ相談しましょう。
まとめ:「湿気は家の天敵! 基礎から対策することで長寿命化」
過去10年ほどの事例を見ても、木造住宅の床下における湿気由来のトラブル(シロアリ被害や木材腐朽、カビなど)は根強く存在しており、施工の丁寧さによって大きな差がついています。日本は湿度が高い気候なだけに、基礎工事の段階から防湿・防水対策を徹底して行うことが、家を長持ちさせるうえで非常に重要です。
「雨漏りのように目に見える水の侵入経路がないから平気だろう」と油断すると、数年後に床下がしっかり湿気を吸い、カビやシロアリの温床になっている可能性もあります。建物自体の長寿命化を考えるなら、基礎の施工写真を確認し、配管周りのシーリングや防湿シートの状態にまで気を配る必要があるでしょう。
実際に住宅会社や工務店へ「防湿シートはどう敷いていますか?」「配管スリーブの防水処理はどのように?」「ベタ基礎の継ぎ目にはどんな施工を?」と質問すると、その対応の仕方が会社の品質管理を映す一面でもあります。誠実な業者であれば、具体的な作業工程や使用材料を示してくれます。
湿気が入り込まなければ、木造住宅は想像以上に長寿命になり得ます。日本においてはシロアリ被害も多いですが、乾燥状態を保てれば被害確率は大幅に下がるという専門家の意見もあります。だからこそ、「湿気を入れない」基礎からの対策が肝心なのです。
家づくりは多くの決断が重なりますが、そのなかでも基礎や床下の見えない部分にこそ大切なポイントがあることを、ぜひ忘れないでください。雨や湿気と上手に付き合い、快適で長持ちする住まいを実現しましょう。
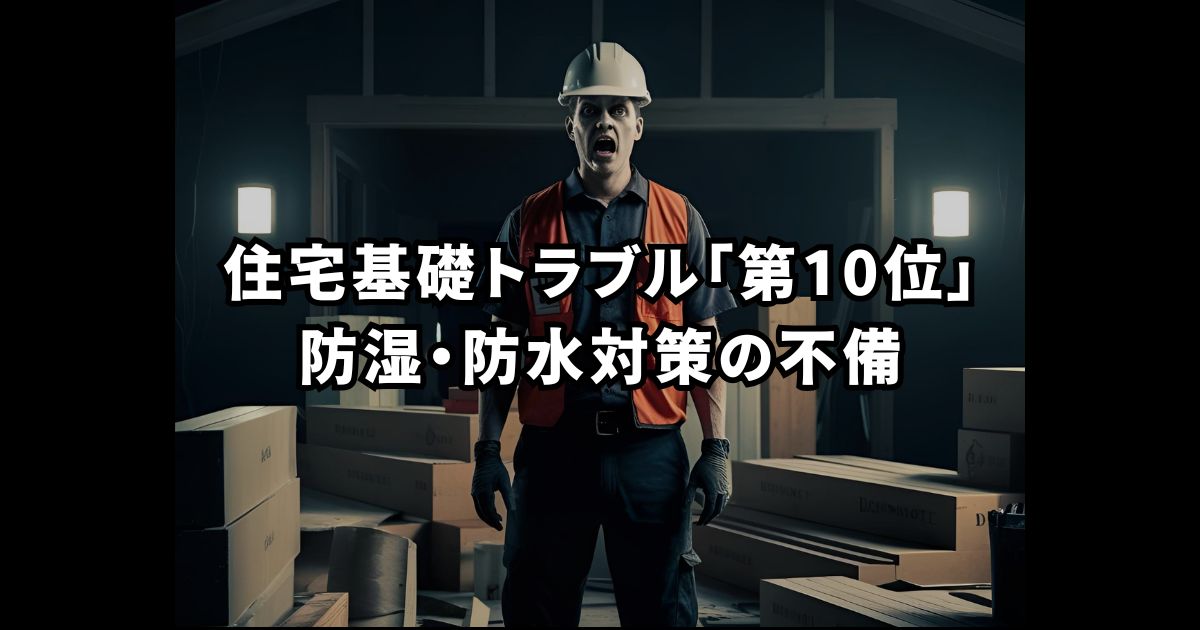

コメント